令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において、家庭連携加算と事業所内相談支援加算が統合され「家族支援加算」が創設されました。
放課後等デイサービス(以下、放デイ)は、家族に対する支援機関としても重要な役割を担っています。
適切に家族支援を行っている事業所は「家族支援加算」を算定することができます。
この記事では、放デイにおける家族支援加算について、制度の概要や算定要件、支援内容の具体例、現場での工夫、保護者との関係づくりまでをわかりやすく解説します。
家族支援加算とは?制度の目的と背景

家族支援加算は、単なる加算項目ではなく、「子どもと保護者を一体として支援する」という放課後等デイサービスの本質を反映した制度です。障がいのある子どもを育てる保護者は、日々の生活の中で多くの不安や孤独を抱えています。療育の場が、子どもだけでなく保護者にとっても“安心して話せる場所”であることは、支援の質を高めるうえで欠かせません。
また、保護者との信頼関係が築かれることで、家庭との連携がスムーズになり、子どもへの支援がより効果的になります。家族支援加算は、こうした“支援の連鎖”を制度的に評価する仕組みであり、事業所の姿勢そのものが問われる加算とも言えるでしょう。
制度の背景:
- 障がい児の育児は、保護者にとって身体的・精神的な負担が大きい
- 支援機関との連携が不十分だと、孤立感や情報不足に陥りやすい
- 保護者への支援を通じて、子どもへの支援の質も高まる
つまり、家族支援加算は「子どもと保護者をセットで支える」ことを制度的に評価する仕組みなのです。
家族支援加算の算定要件とは?
家族支援加算を算定するには、以下のような要件を満たす必要があります。
主な算定要件:
- 保護者に対して、定期的な相談支援や情報提供を行っていること
- 支援内容を記録に残していること(相談記録・支援計画など)
- 児童発達支援管理責任者が関与していること
- 支援が継続的かつ計画的であること
単発の声かけや雑談ではなく、保護者のニーズに応じた支援を「意図的に」「継続的に」行うことがポイントです。
単位数
| 家族支援加算 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|
| 家族支援加算(Ⅰ) | (1)児童の居宅を訪問 | (一)1時間以上の場合 | 300単位 |
| (二)1時間未満の場合 | 200単位 | ||
| (2)事業所等で対面 | 100単位 | ||
| (3)テレビ電話装置等を活用 | 80単位 | ||
| 家族支援加算(Ⅱ) | (1)対面により(他の児童・家族と合わせて) | 80単位 | |
| (2)テレビ電話装置等を活用(他の児童・家族と合わせて) | 60単位 | ||
家族支援加算の算定要件
家族支援加算(Ⅰ)の算定要件
家族支援加算(Ⅰ)は「個別の相談援助」を行った場合に算定できます。(月4回を限度)
家族支援加算(Ⅰ)の(1)の算定要件
居宅を訪問して個別に相談援助を行った場合に算定
■所要時間1時間以上・・・300単位/回
■所要時間1時間未満・・・200単位/回
家族支援加算(Ⅰ)の(2)の算定要件
事業所等で対面にて相談援助を行った場合に算定
■100単位/回 ※30分未満の場合は算定不可
家族支援加算(Ⅰ)の(3)の算定要件
オンラインにて相談援助を行った場合
■80単位/回 ※30分未満の場合は算定不可
家族支援加算(Ⅱ)の算定要件
家族支援加算(Ⅱ)は「グループの相談援助」を行った場合に算定できます。(月4回を限度)
家族支援加算(Ⅱ)の(1)の算定要件
事業所等で対面にてグループでの相談援助を行った場合
■80単位/回 ※30分未満の場合は算定不可
家族支援加算(Ⅱ)の(2)の算定要件
オンラインにてグループでの相談援助を行った場合
60単位/回 ※30分未満の場合は算定不可
家族支援の具体的な内容とは?

では、実際に放デイで行われている家族支援にはどんなものがあるのでしょうか。以下は、現場でよく見られる支援内容の例です。
① 保護者面談・相談対応
- 子どもの行動や発達に関する悩み相談
- 学校や家庭での困りごとへのアドバイス
- 他機関(医療・福祉・教育)との連携支援
② 情報提供・学びの機会
- 発達障がいや療育に関する資料配布
- 保護者向け勉強会・講座の開催
- 支援制度や手続きに関する情報提供
③ 家庭との連携支援
- 家庭での対応方法の提案
- 子どもの様子を共有し、家庭での関わりに活かす
- 保護者の気持ちに寄り添う声かけやフォロー
これらの支援は、保護者の不安を軽減し、子どもへの関わり方を前向きにする効果があります。
現場での工夫|家族支援を“加算”ではなく“信頼づくり”として捉える
家族支援加算は制度上の評価ですが、現場では「加算のため」ではなく「保護者との信頼関係づくり」として捉えることが大切です。
現場での工夫例:
- 面談は“話を聞く場”ではなく“共に考える場”に
- 記録は“義務”ではなく“振り返りと改善”のツールに
- 支援は“情報提供”ではなく“共感と伴走”を意識
保護者が「ここなら安心して相談できる」「子どものことを一緒に考えてくれる」と感じられる関係性が、結果的に加算の要件も満たすことになります。
ICTを活用した家族支援の可能性
最近では、LINEや記録アプリを活用して、保護者との連携をスムーズに行う事業所も増えています。たとえば、記録支援ツールを使えば、以下のような支援が可能になります。
ICT活用のメリット:
- 保護者への報告がリアルタイムで可能
- 記録をもとに面談や相談がスムーズに進む
- 情報共有が簡単になり、支援の質が向上
- 記録が残ることで、加算要件の証明にもつながる
家族支援は“制度”ではなく“文化”として根づかせる
家族支援加算は、制度としては加算額も大きくはありません。しかし、保護者との関係性が深まることで、子どもへの支援の質が高まり、スタッフのやりがいにもつながります。
また、保護者が「この事業所に通わせてよかった」と感じることで、継続利用や紹介につながるなど、事業所運営にも好影響をもたらすことでしょう。
自己評価と保護者評価はTSUNAGUアンケにお任せ!

日々のプログラムや記録などの事務作業に追われる日々。児童発達支援・放課後等デイサービスの自己評価と保護者評価の実施に苦労していませんか?
TSUNAGUアンケは、児童発達支援・放課後等デイ・保育所等訪問支援事業所の評価アンケート代行サービスです。TSUNAGUアンケからお送りする配布用紙データをコピーして従業員様や保護者様に配るだけで、アンケートの集計結果を得ることができます。
集計に係る時間を削減し、事務作業をラクにするTSUNAGUアンケを取り入れてみませんか?
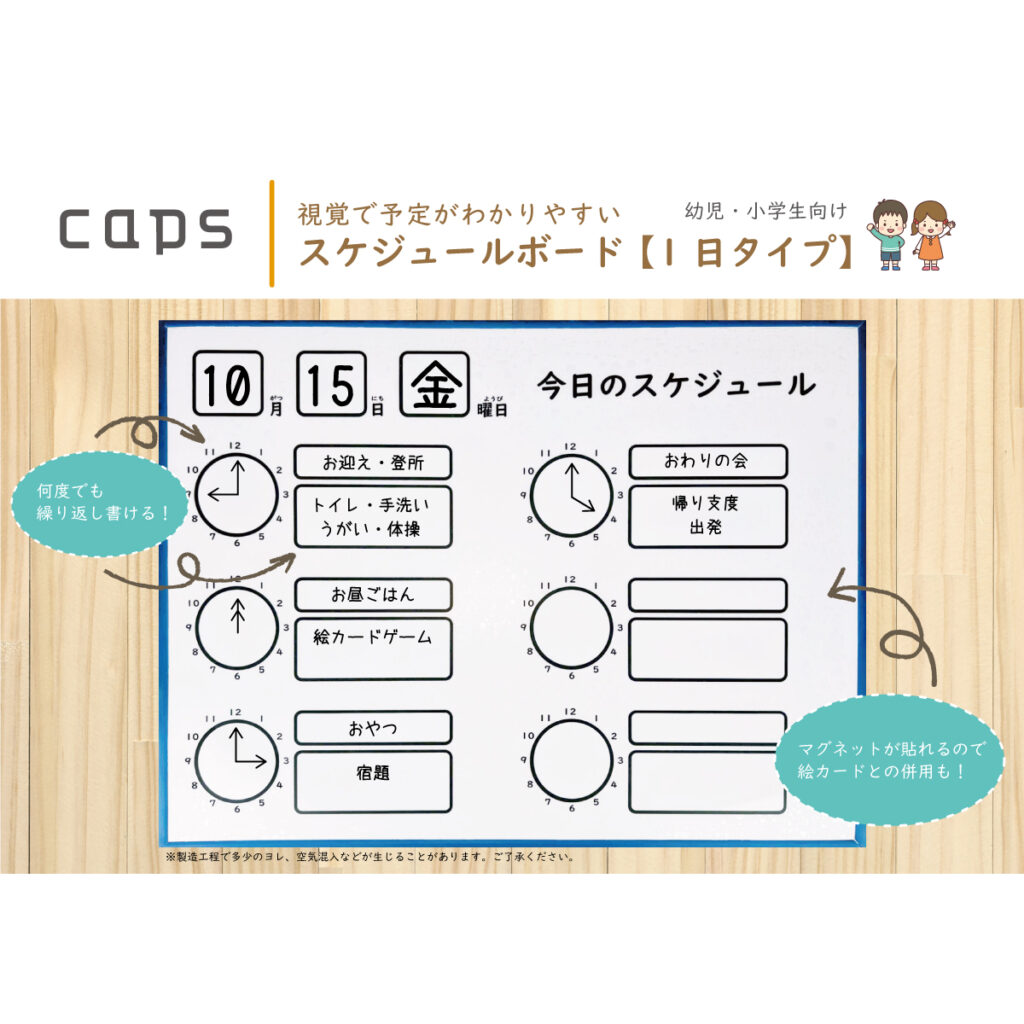
視覚支援に役立つ
スケジュールボード
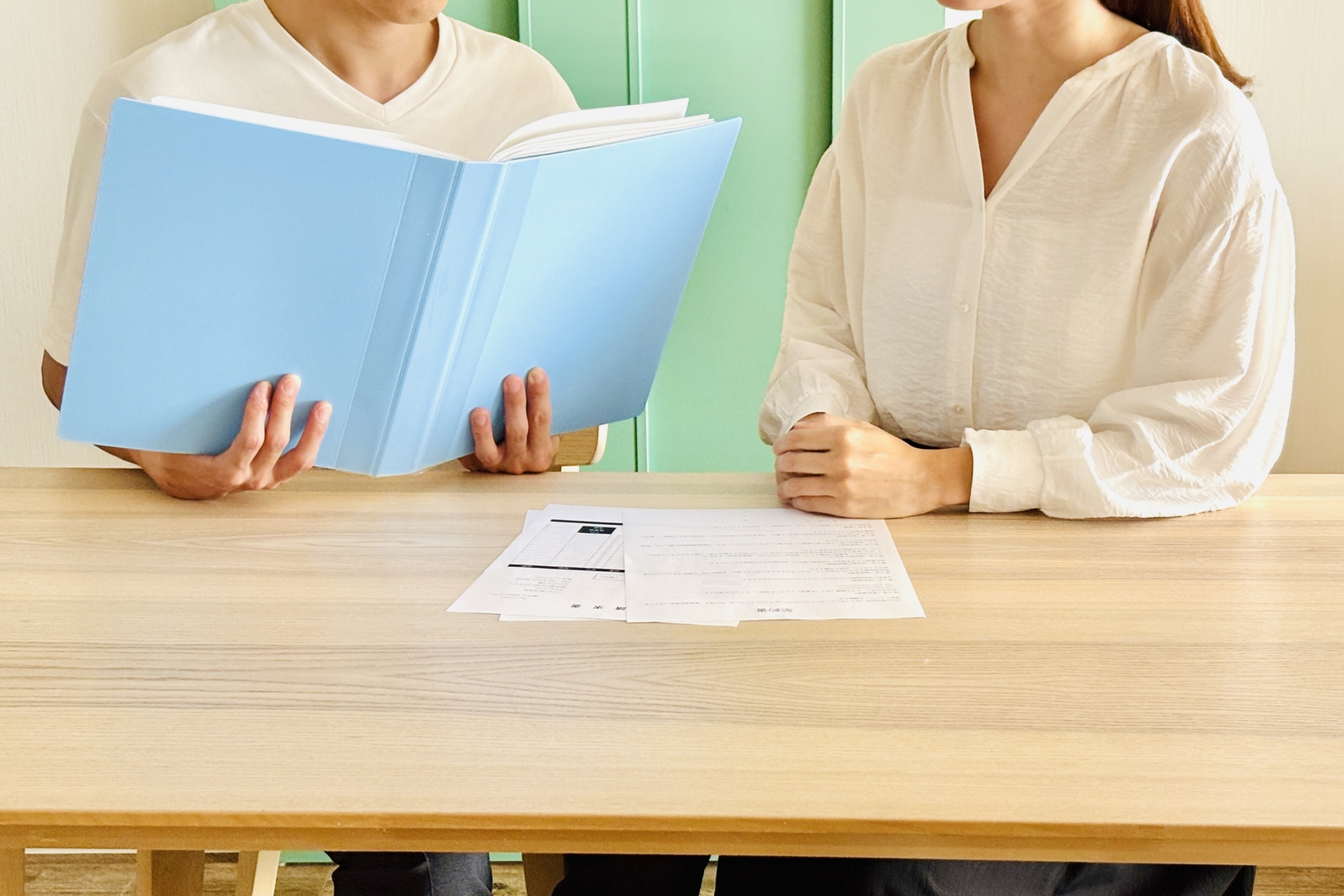


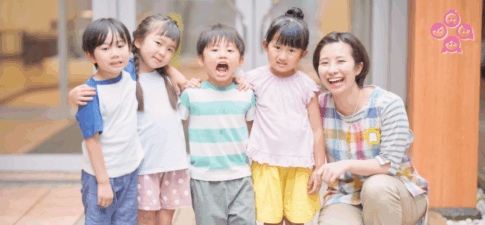







コメントを残す